2025年7月8日放送のEテレ ハロー!ちびっこモンスターのテーマは、「悩めるママパパ大集合!教えて!てぃ先生SP第2弾」です!!
今回は悩めるママパパにてぃ先生が目からウロコのアドバイス☆
「負けず嫌いすぎて困る!」
「ケンカを見ていなかったときどう収める?」
「弟がお姉ちゃんにかみつく!」
といった、お悩みに対して、てぃ先生はどんなアドバイスをするのか!?
さらに街のママパパたちにお悩み調査では、
「だっこばかりで歩いてくれない!」
「突然走り出して危ない!」
「パパとのお風呂を嫌がる!」
「こどもの注意の仕方がわからない…」
など、こんなお悩みをお持ちのママパパ必見の内容でした!
筆者も3歳と1歳を子育て中の身ですので、『なるほど~、さすがてぃ先生だわ!』と明日からの育児に役立ててみたくなりました☆
見逃した方は、放送をまとめたのでぜひ本記事を読んでみてくださいね♪
負けず嫌いのお姉ちゃんが心配…どう接すればいい?

こちらの相談は、「負けず嫌いの子どもがお友達に対しても負けず嫌いを発揮してしまうのでは、と対人関係が心配」という内容でした。
例えば、ゲームをしていて自分が負けそうになると勝手にルールを変えて勝敗を誤魔化してみたり、最後まで遊ぶことができない、なんてこと子育てしているとよくありませんか?
これをおうちだけでなく、お友達にもしていたら…と心配になり、家庭でも厳しく言うべき?なんて悩むことあると思います。
このお悩みに対しててぃ先生は…
負けず嫌いは良い性格!伸ばしてあげたい
負けず嫌いはとってもいい性格だと思います!
チャレンジすることを怖がってしまったり、行動を起こさなくなったり、興味を失ってしまったりすることの方が、お子さんにとって一番もったいないことです。
ママパパはお友達同士の関係で心配があるかもしれないけど、それはそうなったときに本人が考えればいいこと。今から心配していたらきりがないと思う。
今は人との付き合いの中で練習している最中なんだな、人間関係も含めて試行錯誤しているんだな、と受け止めてあげられるといいと思います、とアドバイスされました。
それでもルールを破ったときは?
そのままでOK!
「そのルールにするんだぁ」「それだとママ勝てないなぁ」という受け止め方でいいと思います。おうちの中でも厳しくしてしまうのはもったいないかなぁ。
と、てぃ先生はアドバイスされていました!
つい子どもの人間関係を心配するあまりに、親として正しさを教えるべきなのではと思ってしまいますよね。そんなお悩みに対して、てぃ先生のアドバイスはママパパに寄り添った「このままでいいんだ」と思わせてくれるものでした。
見ていなかったきょうだいケンカを収められない
親が見ていないところできょうだいケンカが勃発すること、あるあるですよね。
相談されたママは「見ていなかったからママわからない」と言ってなあなあにしていて、パパは「どっちが悪いかわからないので、先に手を出した方を怒る」ようにしているとのこと。
見ていなかったらどうしようもないですよね…
そんなお悩みにてぃ先生がしたアドバイスは??
被害者と加害者を決めない
見ていなかったケンカに対して、被害者と加害者を決めないのが鉄則!
見ていなかった以上判断の余地がないので、とにかくお互いの主張を聞く!それしか親御さんにできることはないです。
お互いの主張を聞いたうえで、次は子どもたちの考えを聞くこと。
「○○ちゃんはこうだったんだね」「○○くんはこうだったんだね」「ママはこう思ったんだけど」「2人はそのおもちゃをどうしたらいいと思う?」と話を整理してあげるといいそうです。
きょうだいケンカにはシミュレーションが大事!
これはどういうことかというと、子どもたちは一回やったことは学びやすくなってイメージが付きやすくなるので一回練習しておくというもの。
「ケンカになったらママに教えてね」と伝えておわりにするのではなく、「2人が困ったことになりました!はい、どうするんだっけ!?」と言ったら「ママ―!」と呼ぶ、ということを一度練習しておくと良いということだそうです。
手が出たり、ママパパが望まないトラブルが起きたら、そういうアピールの方法ではなく「こういう方法もあるよ」と伝えると子どもは平和に終わりやすいです。と、てぃ先生はアドバイスされました。
噛みつく癖、どう反応するべき?

次のお悩み相談では、弟がお姉ちゃんに噛みついてしまうということでしたが、どうやらきっかけは【パパに噛みついたら喜んだ】ということで、遊んでいる感覚を持たせてしまったようです。
そりゃ~パパが喜んだら「やってもいいんだ!」と思ってしまいますよね(;´・ω・)💦
その被害に合うこととなってしまった上のお子さんはたまったもんじゃありません。。
下の子が上の子に噛みついたときは「ダメだよ!!」と注意をしていたようですが、笑っていて効果はなかったようです。
そこで、てぃ先生の出したアドバイスは…
場をしらけさせる
まず噛むことは面白くないこと、よくないことだということを根気強く伝えていきましょう。
その伝える方法として、いきなり「噛んじゃダメ!」という言い方になると、お子さんにとっては【噛む】というのが家族とのコミュニケーションの方法になってしまっている以上、それを否定する=家族とのコミュニケーションが否定されることにもなる。
ではどうすればいいのかというと、まずは【場をしらけさせる】。
噛んでも何も面白くないし、「なにやってんの?」「すべってるよ?」くらいのほうが、お子さんにとっては「噛んでも家族は喜んでくれないし、お姉ちゃんも楽しく遊んでくれないんだ」と学びやすくなります。ということでした。
代案を提案する
もう一つの対応としては【代案を提案する】ということです。
例えば、ママが上のお子さんに「ちょんちょん」としてみて、上のお子さんはオーバーに嬉しそうにします。すると下のお子さんは真似してみたくなるでしょうから、実際にやってみると噛みつくよりも「ちょんちょん」した方がお姉ちゃんは喜ぶんだと理解します。
そうすると次からは噛みつくよりもちょんちょんにしてみよう!と移行することができるそうです。
てぃ先生のこのアドバイスによって、こちらのお子さんはお姉ちゃんに噛みつくことがなくなったそうですよ!!
歩けるのに歩かない…どうする?

続いては街のママパパのお悩み相談です!
2歳の女の子のママのお悩みは、お出かけの時に、パパがいると「パパは抱っこしてくれる」と分かっているからか歩けるのに自分で歩こうとしない、パパと一緒でも歩けるなら歩いてほしいというもの。
これについててぃ先生のアドバイスは?
目的地に着くまでの楽しみを用意
歩くのが楽しい時期であれば自分で歩くでしょうが、そうではないと大人と同じで目的地に着くまでは暇になってしまうので、「目的地につくまでの楽しみを用意」するといいです。
例えば、アプリの地図マップでその地点の物や場所の写真が出てくるので、「歩いて行くと銅像があるから、この銅像を探しながら歩いてみよう!」というふうにすると、町中が何かを見つける遊びに変わるというもの。
遊びにできるルールを一緒に考えてやってみると、お子さんが最後まで楽しんで歩いてくれると思う。というアドバイスでした!
危ない!急に走り出す子どもに

続いて、わんぱくな3歳の男の子ママからの相談は、道路の向こう側に自分の気になるものがあると、信号とか関係なく走っていってしまうので追いかけるのが大変という内容でした。
2~3歳児にはあるあるですよね。命にかかわる問題なので親は真剣に怒りますし、なんとかしたいと思います。
これに対して、てぃ先生のアドバイスは?
手をつなぐ習慣をつける
手をつなぐのを嫌がる子に共通していることは、無理やりつながされるということ。
これを手をつなぐ楽しさを教え嫌がらずに手をつなぐ習慣をつけることがポイントになるようです!
その方法は…例えば、「今日のママのおてて温かい?冷たい?」というこの一言でも自分からママの手に触ってみようかなという気持ちになるかもしれません。
あとは、好きなキャラクターのシールを親と子の手に貼って「○○と○○仲良しで歩こうね」と声をかければ、「手をつなごう」よりも「キャラクター同士が仲良し」の方がイメージしやすくなるので、楽しい方法に変えていくのもいいと思いますとアドバイスされました。
これとってもいい方法ですよね!遊び心があって子どもも手を繋がされていると思わなくなり、手をつなぐことの習慣が付きそうです♪
ハーネスを使う
一部ではいろいろと賛否両論あるみたいですが、ハーネスを使うことも命を守るためにはひとつの方法です。
やはりケガをする前に何かしら手だてを打っておかないと、後から後悔しても遅いですから…。とコメントしていました。
パパとのお風呂を嫌がる!どうしたらいいの?
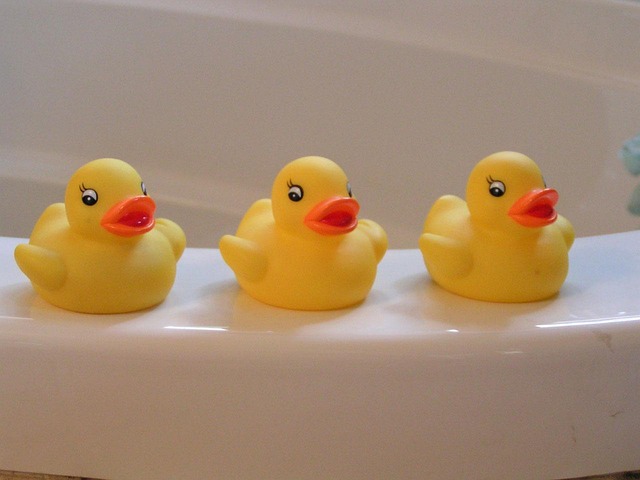
こちらのお悩みは、1歳の女の子のママパパからの相談です。
週末はパパにお風呂をお願いするけど、日頃お世話をしているのがママの方が多ければ、「ママがいい!」「ママじゃなきゃイヤ!」はよくあること。でも、パパだって一生懸命お世話しているのだからちょっと切ない気持ちになっちゃいますよね。
そんなお悩みにてぃ先生のアドバイスは?
最初は3人でお風呂に入ってみよう!
まず、いきなりパパでもいいに持って行くのは諦めた方がいい!と、てぃ先生。
なぜかというと、このくらいの月齢のお子さんだと「ふだんやっている人にふだんどおりにやってほしい」ということに、こだわりや安心感を持っている場合が多いから、ということ。
その安心感という部分で、パパの場合はまだ薄いわけだから、急に「はい」って渡されたら泣いて当然。
そんな時は、最初はパパママとお子さんの3人でお風呂に入ってみよう!!
ママが支えている間にパパが洗ってあげる、と慣れさせてあげることで、徐々にママでなくてもパパでも体を洗うことができるんだなと子どもが慣れていくそうです!
ママという絶対的な安心できる人がいる環境下で、ちょっとずつパパに慣れていくのが一番お子さんにとって負担が少ないと思う、とアドバイスされました。
注意の仕方がわからない!

最後は1歳9ヵ月の男の子のパパからのお悩み相談です。
それは、よくないことをした時の注意の仕方がわからないという内容。
おもちゃを口に入れてしまったり投げてしまったときや、ドアをほうきで叩いてみたり…そんなときママパパはしっかりと「ダメ」や「やめて」と短い言葉で注意されていました。他にも、ベランダに出ようとするときなど、危険なことには力づくで対応されているようです。
注意の仕方を模索しているようですが、伝わっていないと感じているそうです。
特にママの注意は聞くけど、パパの注意は聞いてもらえず…
これに対して、てぃ先生のアドバイスは…
子どもとの信頼関係
子どものことを叱って、それを子どもの中で響く状態にするには、子どもとの信頼関係が必要になります。
普段から子どもとの関わりの中で、「パパのこと好き!」「パパのこと信用できる!」という機会を増やしていくことが、パパにはまず必要です。
言ったことをちゃんと守ることができるようになるのは早くても2歳後半から3歳とかで、仮に子どもがいうことを聞いたとしても、それは何が良くないからやめようではなく、ママパパに叱られたくないからやめているだけで、恐怖や不安からくるもの。だからパパがいなければやってもいいとなってしまうことも。
ただ、ケガや命にかかわることは、しっかりと伝えてやめさせるようにするのは大事なことです。とコメントしていました。
別の案を提案しよう!
では、具体的にどう対応していけばいいのでしょうか?
先ほどのドアをほうきで叩いてしまうときは、「玄関のドアをバンバンするのはやめよう。」「クッションにだったらバンバンしてもいいよ」と別の提案をし、バンバンしたら「バンバン上手だね!」とほめることで、【玄関にバンバンすることは怒られるけど、クッションなら褒めてもらえる!】と自然と別の方法を選ぶことができる、とアドバイスされました。
ただ「ダメ!」と言ってしまうと、『やりたかった』という気持ちをかなえられないままで終わってしまい結局また同じことを繰り返してしまいますが、【これはダメだけど、これは良い】というその方法を具体的に伝えてあげるのがいいと思います。
まだ行動の善悪の理解が難しい月齢のお子さんには、ダメ!と叱ることよりも、こうした方がもっと良いということを教えた方が良いということでした。
てぃ先生のことば
番組最後にてぃ先生の感想がありました。
「総じて言えるのは、ママパパが焦っているんだなということです。」
「みなさんのお子さんはまだまだ小さくて、失敗するのも当たり前の中で、どうしても子どもに失敗させたくない、まわりに迷惑をかけさせたくないという思いが先行してしまうと、悩み自体もすごく早くなる。」
「たくさん失敗をしながら学んでいくって思うことができたら、そもそもまだ悩まなくてもいいのかもしれません。」
とコメントをされていました。
すごくこの言葉は刺さりました。まだこの世に生まれて数年のわが子に対し、ついつい心配をしすぎて悩みが先行しがちだったので、まだ3歳!何にもできない!くらいの気持ちで見てあげたいなと思いました。
おわり
てぃ先生の目からウロコなアドバイスをたくさん聞いて、明日からさっそく試したくなるような内容ばかりでした!!
そしていつも思うのが、番組MCの野々村さんの受け答えがほんわかしてるのに鋭いので大好きです♡
今後もハロー!ちびっこモンスターを見て子育てに生かしていきたいですね!
以上、最後まで読んでくださりありがとうございました!

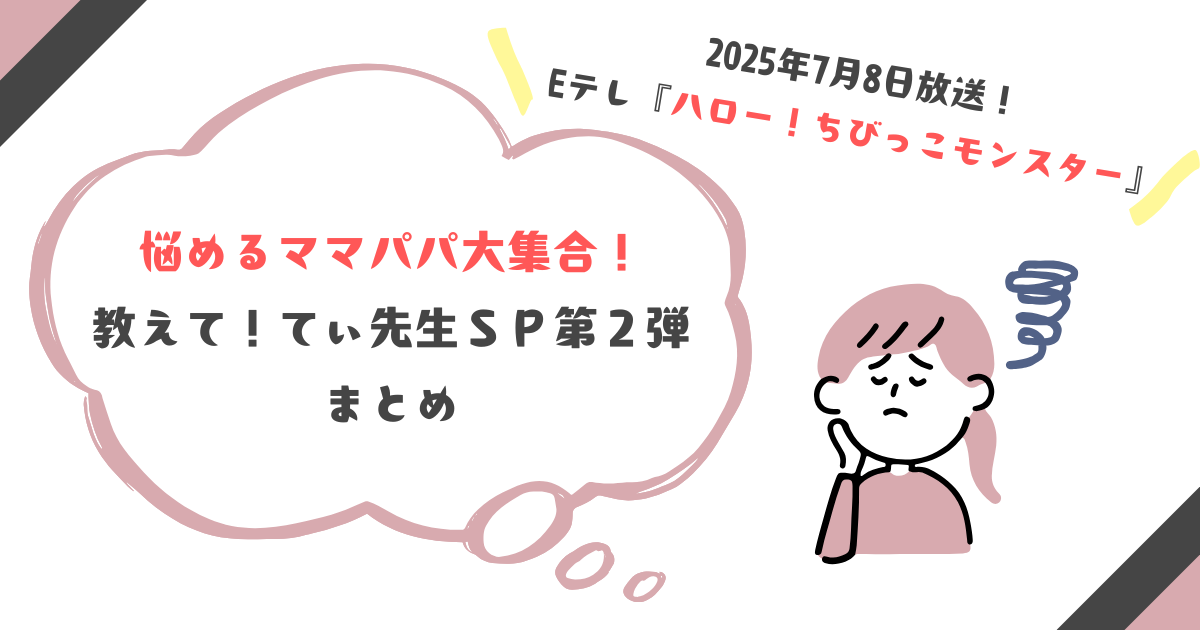
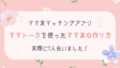
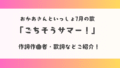
コメント