2025年6月21日午後0:30-午後0:59に放送されたEテレ「すくすく子育て」の今回のテーマは『シン・イヤイヤ期の乗り越えかた』です。
ママパパの心の余裕をうばっていくのが2歳前後の子どもに現れる“イヤイヤ期”。
番組の冒頭では、イヤイヤ期の鉄板の対応と言えば、子どもの気持ちに寄り添うこと、子ども自身に選ばせることなど、「共感的な関わり方」と紹介がありました。
ですが、今回は『シン・イヤイヤ期の乗り越えかた』ということで、誰でもできちゃう対処法に目からウロコ!
絶賛イヤイヤ期中のお子さんや、そろそろイヤイヤ期を迎えようとしているお子さんのママパパは必見です!!
この記事でわかること…
●イヤイヤ期ってどうしてあるの?
●イヤイヤ期はみんなどう対応している?
●イヤイヤ期の新しい対処法!
イヤイヤ期の悩み、イヤイヤ期ってどうしてあるの?みんなどう対応してる?

イヤイヤ期のお子さんを持つママパパのお悩みや、イヤイヤ期がどうしてあるのかを専門家の先生が教えてくれましたのでご紹介します。
イヤイヤ期の悩み
- こだわりが強くなってきたのはイヤイヤ期のせい?
- なにがいやなのかわからない…。
- イヤイヤ期っていったい何なの?
こんなお悩みありませんか?
なにがいやで泣いているのかわからないとどうしていいかわからず、思いつくことは全部やってみてもヒートアップしてママパパはお手上げ状態になることも…。
いったいどうしてイヤイヤ期ってあるの??どうしてあげるのが正解なの?
と多くのママパパが悩む、2歳前後の苦しい時期…。
そんなイヤイヤ期について、専門家の先生が解説してくれました。
イヤイヤ期ってなに?どうしてあるの?
イヤイヤ期のお子さんは心も身体も発展途上中で、自分と相手は心や見え方が違うということを分かっていません、と日本女子大学教授発達心理学 麦谷綾子先生は教えてくれました。
イヤイヤ期は一歩一歩階段を上っているところで、成長の過程において大事な時期です。
また、イヤイヤと自己主張をすることは自分で自分を良くするため、自分をコントロールするためにしていることだそうです。
イヤイヤ期があることの意味がわかると、少し子どもの癇癪に対して気持ちの余裕が生まれますね。
イヤイヤ期どう対処してる?

イヤイヤ期は成長の過程においても大事な時期とわかったけど…その対処法は?
世のママパパはどうしているんでしょうか?
共感・受け入れ
イヤイヤ期の対応として、王道なのは『共感と受け入れ』です。
「嫌だったんだね~」「○○したかったんだね~」「わかるよ~」といった声掛けをして、嫌な気持ちを共感し受け止めてあげるというもの。
これに対して専門家の先生は、
「共感される経験によって相手の思いも受け止められるようになる。
今はダメだよと言われたりして、思い通りにいかないことも学び、自己抑制ができるようになる。」
とコメントしていました。
共感と受け入れることは、イヤイヤ期のお子さんにとって良い対処法ということがわかりますね。
シン・イヤイヤ期対処法!
王道の「共感と受け入れ」で対応してみてもうまくいかないこともありますよね。
むしろ共感をしたくらいで収まってたらイヤイヤ期なんて大したことないです。笑
そんなイヤイヤ期の対処法に新たな考え方を お茶の水女子大学特任教授 保育学 宮里暁美先生が教えてくれました。
1.「あ!〇〇するんだった!」
まず一つ目の新しい対処法は、「あ!○○するんだった!」です。
これは、お子さんがイヤイヤを発動したときに「あ!ママ○○するんだった~!」と言ってその場の空気を変えるというもの。
「あ!洗濯物たたまなきゃ~!」
「あ!ママお茶を飲まなくちゃ!」
「あ~!ママなんだか眠くなっちゃった~」
これでイヤイヤしていたお子さんも、なんとなく空気が変わって、気付いたら癇癪も止まっているというのです。
「何をやってもいやいやが収まらないときは、子どもと真正面から向き合うことをいったんやめてみる。
共感する、願いをかなえるなど対応してみてもうまくいかなかった、煮詰まってしまったときの、次のステップとして提案しました。こういう対応もあるんだと思ってみてください。」
とお話していました。
空気を変えることで、子ども自身の気持ちを立て直すきっかけをつくってあげる、そういう対処法をひとつでも多く持っておくといいですね。
また、番組MCの丸山桂里奈さんは、「娘がイヤイヤ期でめちゃくちゃ泣いたら、自分が鳥になって人間ではなく鳥として考えることで気持ちが落ち着くことがある」とコメント。
こういう考え方もいいですよね。いったん別人格になってみるとママパパ自身もイライラせずに落ち着くことができるかもしれませんし、空気も変わるかもしれません。
2.イヤイヤ物語にピリオドを打つ

イヤイヤが落ち着いたときに「さっきは何がいやだったの?」とすぐに聞くのはNG!
それがきっかけでイヤイヤな気持ちが再びおこる可能性があるので、
終わったことには触れずに、何か一緒にできることを提案するなど、ピリオドを打つ。
子どもが新たな気持ちでスタートできるようにサポートしましょう。
例えば…
「なんだかとっても喉が渇いたね!一緒に冷たいお水を飲もうよ!」
「さっきお外に綺麗なちょうちょがいたから探しに行こうよ!」
「サラダ作るの一緒にやってみない?」
こんなふうに楽しい、嬉しいを共有できたら、イヤイヤ物語完結です。
イヤイヤ期と戦うママパパへ専門家の先生からのアドバイス
番組最後に、イヤイヤ期中のお子さんを持つママパパに向けて、先生たちからコメントがありました。
イヤイヤ期は必ず終わりが来る
「まわりの子と比べて落ち込むこともあるかもしれないけど、あっという間に成長してこのイヤイヤ期は必ず終わりが来ます。発達には変化があると見通しを持ってもらえたらいいと思う。」と、麦谷綾子先生はコメントしました。
イヤイヤ期の度合いはお子さんによって全然違いますよね。
まわりの子と比べて、なんでうちの子はこんなに癇癪がひどいの?と悩むこともあります。
でも、このイヤイヤ期という時期は子どもの長い成長期間の中で1~2年程度です。いつかそんなこともあったねと言えるような日が必ず来るので、見通しを持って子どもと接していきたいですね。
子どもを追い詰めない・親も思いつめない
「子どもを追い詰めない・親も思いつめない。気分をちょっと変えてみて、素敵な人になっていくために大事ないまを葛藤しているんだと思ってみてください。」と宮里暁美先生はお話していました。
宮里先生の「子どもを追い詰めない・親も思いつめない」という言葉はとても心に響きました。
いつか終わりが来るとわかっていても、いま日常の中で起きているイヤイヤ期との戦いで、つい先が見えなくなり「どうして??どうすればいいの??」と思いつめてしまうことがあると思います。
そんなときは、空気をちょっと変えてみたり、子どもと向き合うのをいったんやめてみることで、思いつめていた気持ちをほどいてあげられるといいですね。
おわり
イヤイヤ期って最初は戸惑いますよね。
いままでこちらの都合でなんの問題もなくお世話をしていたのに、何もかもイヤ!といって進めさせてもらえなくなる。
可愛かったわが子が急に憎らしくなったりして、かなり困惑します。
イヤの気持ちに共感してみたり、受け止めてみても、そんなもんじゃ収まらないのがイヤイヤ期です。
ママとパパも人間ですから、完璧にこのイヤイヤに応えることはできないですよね。
向き合わないということも選択肢のひとつとしてもっておくと、こちらも心の余裕が生まれ、結果として子どもとの関係も好転していくのではと思いました。
3歳7か月の長男はすでにイヤイヤ期を終えていますが、次は1歳の次男か~!と怯えています。
なんとなく下の子の方が手ごわそうなので、私も「あ!○○するんだった~!」作戦で乗り越えていきたいなと思います!
以上、「すくすく子育て『シン・イヤイヤ期の乗り越えかた』新たな対処法でイヤイヤ期を乗り越えよう!」でした。

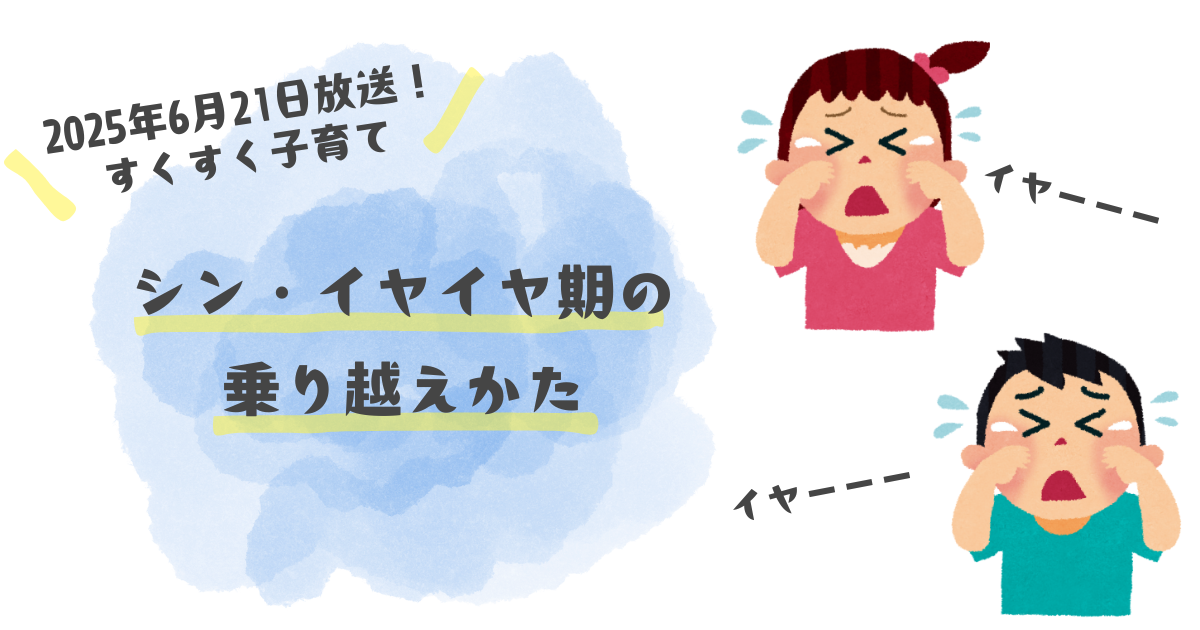
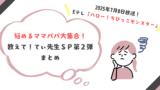
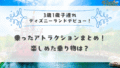
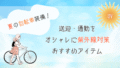
コメント